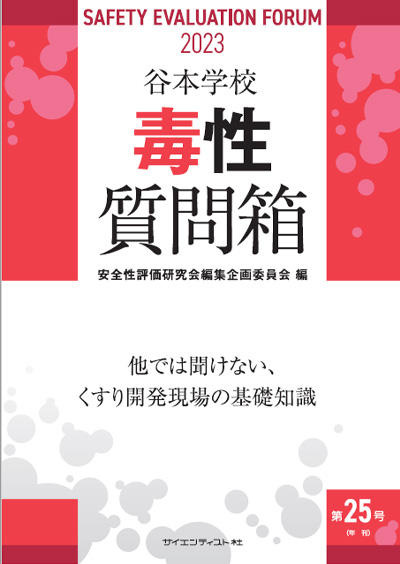谷学発!常識と非常識 第82話 生命の起源と進化⑫
――ダーウインの時代には扱えなかった4つの進化の謎
ダーウインが『種の起源』を書いたのは160年以上も昔のことであり、当時の科学の水準では扱えなかった進化の謎がいくつもありました。今回はその中から4つを取り上げます。
1.原核細胞はなぜ真核細胞に進化したか?
約40億年の生命の歴史の前半の約20億年は、原核生物(細菌類)だけの世界でした。原核細胞は核膜もリボソーム以外の細胞小器官も持たず、構造が単純ですが、約20億年前に突然誕生した真核細胞は、二重の核膜とミトコンドリアなど各種の細胞小器官を持ち、構造が複雑です。
カリフォルニア大学のリヴェラらは、真核細胞の起源を明らかにするため、真核細胞の遺伝子を解析し、DNAの複写や翻訳に関わる「情報系遺伝子」は古細菌由来であり、エネルギー産生に関わる「代謝系遺伝子」は真正細菌由来であることを明らかにし、真核生物が古細菌と真正細菌の融合によって生まれたと考えました(※1)。
一方、ドイツのマーティンらは、水素の欠乏が原核細胞から真核細胞への進化をもたらしたとする「水素仮説」を提唱しました(※1)。この仮説によれば、約27億年前に光合成細菌のシアノバクテリアが偶然に誕生し、老廃物の遊離酸素を放出し始めたため、それまで遊離酸素が存在しなかった地球環境が、数億年かかって遊離酸素が豊富な好気的環境に移行しました。このとき、生存のために水素を必要とした嫌気性細菌の多くは絶滅しましたが、一部は水素が豊富な深部地下や海底熱水噴出孔付近で生き残りました(※2)。また、二酸化炭素を水素で還元してエネルギーを獲得し、老廃物としてメタンを排出する古細菌の1種のメタン生成菌は、老廃物として水素を排出するα-プロテオバクテリアを細胞内に共生させて生き残りました(※1)。
約20億年前、この共生体が核膜を形成して真核細胞に進化し、共生していたプロテオバクテリアはミトコンドリアに進化したと考えられています(※3)。すなわち、原核細胞から真核細胞への進化は、シアノバクテリアの繁殖による嫌気的大気から好気的大気への転換という地球環境の大激変に、原核生物の一部が適応しようとしたため起きたと考えられます。また、生存のために水素を必要とした2種の細菌、OD1とメタン生成菌の生存戦略や、無数の生きた化石生物の存在から、私見ですが、進化に関する次の2つの仮説が浮かび上がります:①生物は生存可能な環境が続く限り、何十億年でも進化しない。②生物が進化するのは、新しい環境に適応するときである。
2.単細胞生物は不老不死化か?
単細胞生物は分裂して増殖するので、かれらは永遠の生命を持つという人もいます。しかしこれは誤解で、微生物も不老不死ではありません。細菌類も個体単位で見れば当然死にます。細菌類はアメーバなどの原生生物に捕食され、栄養不足でも紫外線や高熱でも死にます。大局的に見て全ての生物の個体数が殆ど一定である理由は、個体の増加数と死亡数がほぼ等しいからです。
また、単細胞生物にも寿命があることは、ゾウリムシで確認されています。ゾウリムシを分裂のたびに分離して個別飼育すると、やがて分裂しなくなり、全滅します(※4)。ゾウリムシが増殖し続けるには接合が必要です。接合は極めて複雑な過程です。接合により2匹のゾウリムシの細胞質が部分的に連続し、小核が2回減数分裂して4個になり、うち2個が消失し、残った小核の一方を接合相手と交換した後、接合が終わり、大核が消失し、小核が合体した新小核から大核と小核が再生されます。接合は異なる型の個体の間でのみ起こる、一種の有性生殖であり、多細胞生物の有性生殖と同様に、ゲノムの再生の過程と考えられています(※4)。
なお、我々ヒトを含む多細胞生物も、個体に注目すれば生命は有限ですが、生殖細胞やその遺伝子に注目して祖先をたどれば最初の生命にまでたどり着く点では単細胞生物と同じです。
3.多細胞生物はなぜ生まれたか?
単細胞生物が分裂後に分離しなければ容易に多細胞生物になるため、生物は様々な利益のために多発的に多細胞化したと考えられます。多細胞化することにより生物は巨大化し、様々な組織や器官を分化させ、生命活動を効率化しました。多細胞化の最大の利点は、本格的な有性生殖を進化させたことにあると考えられます。有性生殖は単細胞生物の分裂増殖と比較すると、個体の半数のオスが子供を産まないため、非効率に見えます。しかし、有性生殖の最大の目的は、ダーウイン的進化を促進させるために、子孫の個体変異を最大化させることにあると考えられます。
個体変異増大の仕組みは2種類知られています。1つは配偶子(精子と卵子)形成の際の減数分裂の過程で、父方と母方の染色体が交差し、遺伝子組み換えが起こることです。同じ親から生まれた子共たちでも、顔や性格が異なるのはこのためです。個体変異の最大化のもう1つの仕組みは、個体の移動や植物では花粉の風媒・虫媒により、地理的に離れた配偶相手との生殖(混血)を可能にしたことです。混血の結果、子が親よりも優れた形質を持つ現象が「雑種強勢」です。
早川智氏は有性生殖の最大の目的は、種内の個体変異を増大させることにより、短期間で変異する感染性微生物やウイルスとの闘いに生き残る可能性を高めることにあると考えています(※5)。例えば新型コロナウイルスCOVID-19感染後のヒトの反応は、全くの無症状から死亡まで多様であり、人類が個体差によってパンデミックに対抗し、生き残ってきたことが分かります。
4.進化する生物と「生きた化石」生物が存在するのはなぜか?
硬骨魚のシーラカンスは約4億年、節足動物のカブトガニは約2億年、その形を殆ど変えていないので、生きた化石と呼ばれます。しかし、生きた化石と呼ばれなくても、出現以来数億年以上、殆ど変化していない生物種は無数にいます。その代表が細菌類。出現以来約40億年間、原核生物のままであり、サイズも一定です。また、アメーバなどの単細胞の原生動物は約10億年、カイメンなどの原始的多細胞生物、クラゲなどの腔腸動物、プラナリアなどの扁形動物、ミミズなどの環形動物なども大部分は数億年形を変えていません。我々はこれらの生物を「進化途上の原始的生物」と見做しがちですが、それは大きな誤解であり、かれらが数億年以上も変化しない理由は、これらの生物が太古の昔に既に完成されていて、進化する必要が全くなかったからと考えるべきでしょう。なぜなら、何億年もの間には当然ゲノムに無数の突然変異が起こったはずで、進化する必要があればその機会はいくらでもあったはずですが、新しい環境に進出したごく一部を除き、大部分は何億年も進化していないからです。
これらの「生きた化石生物」が種として何億年も安定している理由の一つは、かれらが変温生物であることです。変温生物は概して、我々恒温動物よりも、遥かに広い環境変化に耐えます。その証拠に、細菌類や原生生物類は約6億年前までの先カンブリア紀に3回あったと言われる「全球凍結」(第74話参照)に耐えて生き残っています。また、多細胞の生きた化石生物たちも、カンブリア紀から現在までの約5億年間に、地球規模の火山活動や巨大隕石の落下などの天変地異による少なくとも5回の生物の大量絶滅にも耐えて生き残っています(第75話参照)。
以上の考察から、進化する生物と生きた化石生物が存在する理由は、第1項で挙げた進化に関する2つの仮説、「①生物は生存可能な環境が続く限り何十億年でも進化しない。②生物が進化するのは新しい環境に適応するときである」によって、うまく説明できます。
(第83話からは人類の進化を取り上げます)。
(馬屋原 宏)
引用文献
- 1)長谷川政実:『進化38億年の偶然と必然』、図書刊行会(2020)
-
2)佐藤友彦ら:冥王代の生きた微化石OD1と超還元場の歴史、地学雑誌128(4)571-596(2019)
doi:10.5026/jgeography.128.571
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jgeography/128/4/128_128.571/_pdf - 3)ニック・レーン:『ミトコンドリアが進化を決めた』、斎藤隆史訳、みすず書房(2007)
- 4)Douglas L Chalker:Keeping one's sex. Nature Digest,Vol. 11 No. 8,doi: 10.1038/ndigest.2014.140827
- 5)早川智:性はなぜあるのか―進化生物学の視点からhttps://www.jstage.jst.go.jp/article/numa/72/3/72_126/_article/-char/ja/







 Today:
Today: